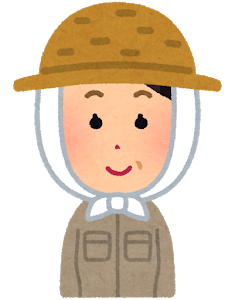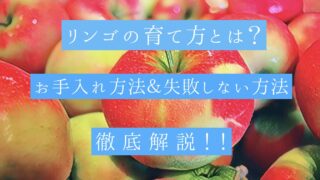今回は「ダイコン」の育て方が気になるって思いませんか?
重要なポイントを知ることで
凄く美味しいダイコンができるって知ってましたか?
美味しいダイコンを作るコツは、土をしっかり耕すことなんです。
ダイコンは手順を守れば、初心者でも簡単に作れますよ。
タネまきから2〜3ヶ月後に収獲できるので手軽に始められますね。
農家の息子と結婚し、子育てをしながら、田舎に移住歴3年の私が
畑で作る「ダイコン」の育て方とは?お手入れ方法&失敗しない方法を含めて解説していきます。
さあ、準備を始めていきましょう。
ダイコンの育て方

基本情報
| 分類 | アブラナ科 |
|---|---|
| 発芽地温 | 25℃前後 |
| 生育適温 | 20℃前後 |
| 日当たり | 日なた |
| 土壌酸度 | pH 5.5〜6.5 |
最低限の準備
| ダイコンのタネ | 市販、通販 |
|---|---|
| 土(石灰あり) | 苦土石灰、堆肥 |
| 害虫対策 | 防虫ネットなど |
| おすすめの肥料 | 化成肥料など |
| あると便利なアイテム | クワ/ビールかジュースのびん(タネを植えるときの溝をつけるため)/マルチシートなど |
ダイコンは、直まきのみになります。移植すると、根が分かれてしまいます。
何を育てるか迷ったら ダイコンの種 タキイネット通販より
土のこだわり方のポイント

ポイント1 深くやわらかく耕す
・使用する肥料
| 苦土石灰 | 1㎡あたり100〜150g |
|---|---|
| 元肥 | 1㎡あたり堆肥2kg、化成肥料100g |
ポイント2 障害物を取り除く
タネまき

ダイコンの「お手入れ方法」
水やり
 発芽するまでは、毎日に水を与えましょう。タネを植えた直後は、タネが水で流れやすいです。優しく水やりをしましょうね。
発芽するまでは、毎日に水を与えましょう。タネを植えた直後は、タネが水で流れやすいです。優しく水やりをしましょうね。
発芽したら、日光をしっかり当てるために、稲わらや不織布は取り除きます。水やりは、土の様子を見ながら調整します。ダイコンは多湿を嫌うので水のやりすぎに気をつけましょう。
| 発芽前 | 乾かさないように水をしっかりやる |
|---|---|
| 発芽後 | 土が乾いたらたっぷりと水をやる |
温度と湿度
ダイコンは、発芽地温25℃前後で、生育適温20℃前後です。
涼しい気候が大好きですが、10℃以下になると花芽が出て、根が太らなくなります。
寒い地域では、11月上旬までに収穫しておくといいですね。
間引き・追肥・土寄せ

間引きが遅れると、生育後期に葉が茂り、根が痩せてしまいます。
間引きのタイミングで、必ず追肥をしましょう。
おすすめ肥料
「ボカシ肥」「マイガーデンベジフル」
害虫対策

ダイコンは、土の上にいる虫と土の中にいる虫の対策が必要です。
土の中にいる虫では、コガネムシの幼虫がよく出ます。根を食べてしまうので「ダイアジノン」という農薬を土に混ぜておくことをおすすめします。
虫が薬に当たって死滅するタイプの薬で、作物に吸収されないです。農薬に抵抗がある方も使いやすいですね。
土の上にいる虫はでは、アオムシ、アブラムシなどがダイコンの葉を食べます。
葉がたくさん食べられると、光合成ができなくなるので、ダイコンが痩せてきます。
タネまきのときに「アクタラ粒剤」(1㎡あたり4g)をまくことをおすすめします。使い方は、土作りのときに溝にまいて、土をかぶせておきます。
よく出る害虫
| アオムシ | 葉を食べてしまう。対策は、捕殺する。防虫ネットで覆う。レタスやにんじんを一緒に育てる。(アオムシが嫌いな野菜のため) |
|---|---|
| ヨトウムシ | 夜に活動し、食欲旺盛なので葉を食べてしまう。対策は、卵のうちに除去するか、防虫ネットで覆う。 |
| コナガ | 対策は、卵のうちに捕殺する。防虫ネットで覆う。キク科(レタス、春菊など)、セリ科(にんじん、セロリなど)の野菜をコナガは嫌うので、その野菜を一緒に育てる。 |
| アブラムシ | 湿度の高い時期に出やすい。対策はダニがいない土を選ぶこと。(市販の培養土ならOK!堆肥は、ダニが入っている場合があるので注意が必要) |
| ダイコンサルハムシ | 体長4mm、葉を食べる。対策は、捕殺する。そして、成虫は反射する光を嫌うので、マルチシートを敷くか、銀色の反射テープを使うと良い。ニラの匂いが嫌いなので、一緒に植えるのもおすすめ。それでもたくさん発生したら、農薬の「べニカ水溶剤」を使うのがおすすめ。 |
| キスジノミハムシ | 成虫は葉を、幼虫は根を食べる。農薬を使う場合は、ダイアジノンがおすすめ。 |
病害虫の対策に困ったら
コンパニオンプランツのメリット
①空いたスペースの有効活用
畑の空いたスペースには、雑草が生えやすいですが、そこを無駄なく使用できます。
②病気や害虫の予防
虫や微生物には好きな野菜が決まっています。だから、それらが嫌いな野菜を植えると、虫や微生物の増殖を防ぐことができるのです。
③野菜がよく育つ
例えば、マメ科の植物の根には、根粒菌が共生しています。そして、空気中の窒素を固定して、植物に供給する性質があります。だから、野菜と一緒に植えると、マメ科の植物が作った栄養を、他の野菜に使うことができます。そのため、作物がよく育つのです。
連作障害
連作障害とは
畑に同じ野菜を続けて作ると、雑菌が繁殖したり、栄養が枯れてうまく育たなくなること。
収穫時期は2〜3ヶ月
うまく育たないとき

これまで、育て方やポイントを解説しました。
ダイコンで失敗しやすいのは、収穫時期が遅れて、スが入ってしまうこと。もう一つは根の下に障害物があって、根が分かれてしまうことです。それは、早めに収穫することや、土をよく耕しておくことで簡単に解決できますね。
ダイコンはスーパーで買ったものでも、辛みや苦味が強いものがありませんか?
私は、今までずっと不思議に思っていました。
同じダイコンで見た目は変わらないのにどうして?
野菜作りを始めて、その原因に気づいたので紹介します。
ダイコンはストレスを受けると、辛味成分のグルコシノレートを出します。ストレスとは、暑さ、乾燥、加湿、病気や害虫などが含まれます。
まとめ

ダイコンは、畑を耕す大変さを乗り越えたら、その後のお手入れは簡単ですよ。
とにかく、最初の土づくりを頑張ることが大切です。
ダイコンは保存がきくし、いろんなお料理に使えますね。
お肉や魚と炊いたり、サラダにしたりと自分で育てたダイコンを食べるのが楽しみですね!
そして、よく育ったダイコンを引き抜く瞬間は、とてもワクワクしますよ。
我が家でも、娘が「よいしょ〜」といいながら、一生懸命にダイコンを引き抜く姿がとても可愛かったです。
子育て中の方は、子どもとの大切な思い出や、食育にもつながりますよ。
ぜひ、その感動を体験して欲しいので、今からダイコン作りを始めてみませんか?
- 害虫対策を必ずする
- トウ立ちしにくい品種を選ぶ
- 土づくりのときは深く耕す
- 早めに収穫する